
About
研究室について
文化財保存学とは、人類の辿ってきた情報が内包された文化財を、歴史学的に、技法材料学的に、自然科学的に、地域社会学的に調べ、文化財の有する本質的な価値や意義の考察、研究に基づいて、未来へ継承していくための保存修復を実施することを探求する学問領域です。文化財保存学保存修復研究室では、様々な表現形態からなる文化遺産のうち、仏像、神像、近代彫刻、キリスト教彫刻、考古遺物などの国内外の彫刻文化財を対象とした文化財の保存修復に関する研究を行っています。
研究室の理念

文化財には、制作当時の情報、現代に伝わるまでに付加した情報が内包されています。それらの情報を調べることが、文化財が有する本質的な価値を図るために必要となります。文化財のもつ情報の適切な把握には、文化財が有する歴史性、芸術性、宗教性、地域性、民俗性などの様々な観点による多角的な考察を行わなくてはなりません。そのためには、文化財の形状、使用材料、構造技法、表現技法、文字資料、付属資料(納入品や奉納札、寄進状等)などを歴史学(歴史学・美術史学・郷土史学・民俗学・宗教史学・考古学など)的に、技法材料学的に、自然科学的に、地域社会学的に調べていくことが重要となります。また、文化財が設置されている場所の温湿度、虫菌害、空気汚染などの保存環境とともに、社会的背景についても検証しなければなりません。彫刻文化財は、木・漆・土・金属・石・顔料・染料・膠着材・接着剤などの様々な素材を加工して制作されてきましたが、制作後に補われた修理の歴史も含めて検証していくことが重要となります。
メンバー
教員

木製彫刻文化財の保存修復を専門とし、仏像、キリスト教彫刻、古代エジプト木製品などの保存修復を数多く手がける。また、地域文化財の保護活動にも取り組み、各地での地域文化財調査や地域現場での臨床的な保存修復活動、防災や被災文化財の保存修復活動なども行っている。
| 1975年 | 愛知県蒲郡市生まれ |
|---|---|
| 1998年 | 東京藝術大学美術学部彫刻科 卒業 |
| 2000年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻 修士課程修了 |
| 2004年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻 博士後期課程 修了 博士号(文化財)取得 |
| 2004年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻研究室 非常勤講師 |
| 2007年 | 文化財保護・芸術研究助成財団在外研修員としてイタリア・フィレンツェのUniversità Internazionale dell’Arte(国際芸術大学)とOpificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze(国立フィレンツェ貴石加工所および修復研究所) にて研修 |
| 2009年 | 東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター 専任講師・研究員 |
| 2012年 | JICA短期派遣専門家(大エジプト博物館保存修復センター人材育成プロジェクト木材研修担当講師) |
| 2015年 | 木製彫刻文化財保存修復研究所 設立 代表 |
| 2016年 | 一般社団法人木文研 代表理事 |
| 2015年 | JICA短期派遣専門家(大エジプト博物館保存修復センター人材育成プロジェクト テクニカルアドバイザー) |
| 2014年 | 山形大学地域教育文化学部 非常勤講師 |
| 2016年 | 大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト テクニカルチーフアドバイザー |
| 2019年 | 帝京大学文化財研究所 准教授 |
| 2021年4月〜 | 現職 |

| 1988年 | 国立小山工業高等専門学校 機械工学科 卒業 |
|---|---|
| 1990年 | (株)仏教造形研究所 入所 |
| 1994年 | 東京藝術大学 美術学部 デザイン科 卒業 |
| 1997年 | 東京藝術大学大学院 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室 修了 学位取得制作「滋賀県近江八幡市伊崎寺 焼損天部立像 想定復元制作」 (サロン・ド・プランタン賞受賞) |
| 1998年 | (株)仏教造形研究所 彫刻部主任研究員着任 |
| 2002年 | あきかわ造仏所設立 神奈川県川崎市文化財調査員(~2010年3月まで) |
| 現在 | あきかわ造仏所代表 長岡造形大学 非常勤講師(2012年4月~) 東京藝術大学 非常勤講師(2021年4月~) |

| 1968年 | 愛知県に生まれる |
|---|---|
| 1986年 | 日本伝統工芸士 吉田信久氏(富山県井波町)に師事 |
| 2001年 | 第9回木彫フォークアート.おおや(兵庫県)グランプリ受賞 |
| 2006年 | 個展「時の旅・風の景 杉浦誠展」(Lギャラリー) |
| 2009年 | 個展「—鳥の視点-杉浦誠木彫展」(靖山画廊) |
| 2011年 | 東京藝術大学大学院保存修復彫刻研究室 非常勤講師(現在〜) |
| 2012年 | 個展「杉浦誠木彫展」(大丸心斎橋店) |
| 2013年 | 個展「杉浦誠木彫展-鳥の視点-」(日本橋三越本店) |
| 2016年 | 個展「杉浦誠彫刻展」(仙台三越) |

| 1984年 | 香川生まれ |
|---|---|
| 2014年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復(彫刻)博士後期課程 修了 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 教育研究助手 |
| 2016年 | 合同会社 藤白彫刻研究所 運営 |
| 2017年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 非常勤講師 |
| 2021年 | 同研究室 テクニカルインストラクター |
| 2022年 | 同研究室 非常勤講師 |

| 1985年 | 神奈川生まれ |
|---|---|
| 2010年 | 東京藝術大学美術学部 芸術学科 卒業 |
| 2013年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 芸術学専攻 修了 平山郁夫奨学金 受賞 |
| 2016年 | 日本学術振興会 特別研究員(DC2) |
| 2019年 | 早稲田大学図書館資料管理課 特別資料室 常勤嘱託(専門職) |
| 2020年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 美術専攻 博士(学術)修了 あさかぜ賞 受賞 東海大学 非常勤講師 |
| 2021年 | 日本学術振興会 特別研究員(PD) 駒澤大学 非常勤講師 |
| 2022年 | 成城大学 非常勤講師 東京藝術大学 学術インストラクター |

| 1981年 | 東京生まれ |
|---|---|
| 2008年 | ロンドン藝術大学セントラル・セント・マーチンズ ガラス&ファインアートコース 准修士修了 |
| 2009年 | ロンドン藝術大学セントラル・セント・マーチンズ ガラス&アーキテクチャーコース 准修士修了 |
| 2010年 | Pierre Mesguich Mosaik Ltd モザイクデザイン、制作工房勤務 |
| 2015年 | シティ&ギルド・ロンドンアートスクール 保存修復科 入学(BA Hon) |
| 2017年 | 大英博物館 石造修復室 インターンシップ |
| 2018年 | シティ&ギルド・ロンドンアートスクール 保存修復科 修了(BA Hon) |
| 2018年 | ビクトリア&アルバート美術館 彫刻修復室コンサバター |
| 2020年 | Taylor Pearce Conservation Ltd オブジェクトコンサバター |
| 2022年 | 東京国立博物館 保存修復室非常勤職員 (一年任期) |
| 2024年 | 東京藝術大学 保存修復彫刻研究室 テクニカルインストラクター |

| 1984年 | 東京生まれ |
|---|---|
| 2007年 | 早稲田大学第二文学部 卒業 |
| 2010年 | 東北芸術工科大学 美術史・文化財保存修復学科 卒業 |
| 2012年 | 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科芸術文化専攻保存修復領域 立体作品修復室 修士課程修了 |
| 2012年 | 有限会社 東北古典彫刻修復研究所入所 |
| 2017年 | 一般社団法人 木文研入所 |
| 2020〜年 | フリーランスの保存修復家として活動 |
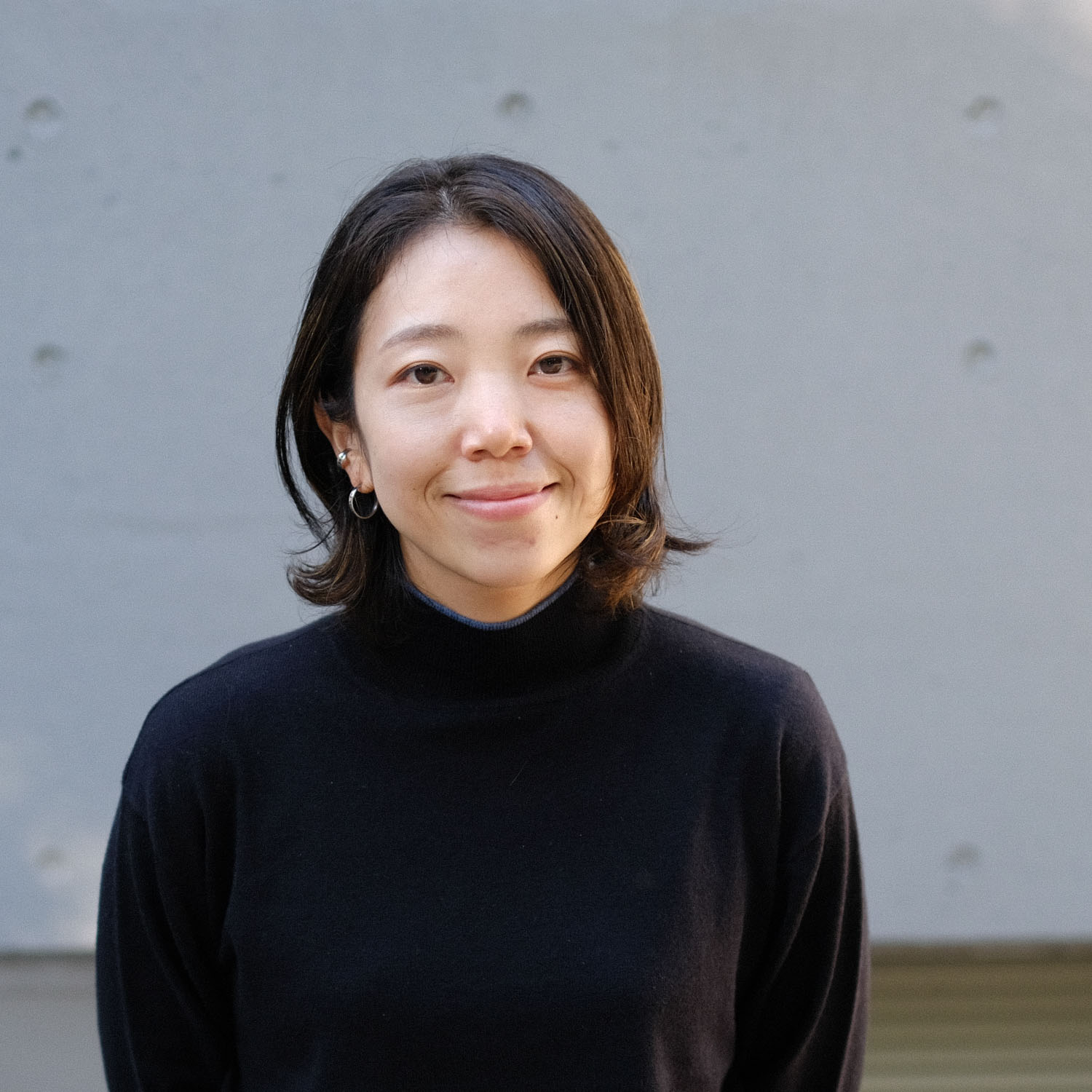
| 1988年 | 東京で生まれ長野に移住する |
|---|---|
| 2014年 | 東京藝術大学美術学部 彫刻科 卒業 卒業制作『そこに居る』東洋文庫賞受賞 |
| 2016年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程在籍 同研究室 研究協力者 |
| 2021年 | 同研究室 教育研究助手 「MITSUKOSHI ✕ 東京藝術大学 夏の芸術祭 2018」作品出品 「MITSUKOSHI ✕ 東京藝術大学 夏の芸術祭 2020」作品出品 フリーで作家活動をはじめる |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 教育研究助手 |
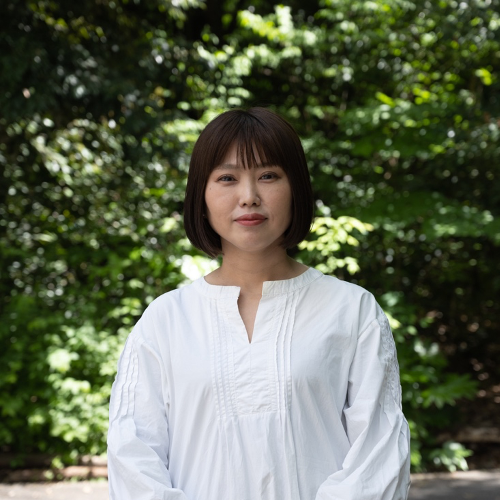
| 2001-2005 | 一橋大学 経済学部 経済学科 |
|---|---|
| 2011-2014 | 東京藝術大学 美術学部 芸術学科 |
| 2014-2016 | 東京藝術大学 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復(油画)修士課程 |
| 2017-2019 | 日本学術振興会 特別研究員(DC2) |
| 2016-2021 | 東京藝術大学 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復(油画) 博士後期課程 あさかぜ賞受賞 |
| 2021-2022 | 東京藝術大学 学術インストラクター |
| 2021-2022 | 文化庁新進芸術家海外研修制度 研修員(ギリシャ) |
| 2021- 現在 | University of West Attica, Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, 研究員 |

| 1986年 | 広島生まれ |
|---|---|
| 2006年 | 東京藝術大学美術学部彫刻科入学 |
| 2010年 | 三菱地所賞受賞
「藝大アーツin東京丸の内三菱地所賞受賞者作品展」(丸ビル/東京) 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻保存修復(彫刻)入学 |
| 2011年 | 「台湾国際木彫藝術交流展」招待出品 |
| 2012年 | お仏壇のはせがわ賞受賞 |
| 2013年 | 「覚の会」(靖山画廊/東京) |
| 2014年 | 「木の系譜―進化する奔流―」(髙島屋/日本橋・大阪・横浜) 「籔内佐斗司とその後継者たち」(松坂屋/名古屋) |
| 2015年 | 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻保存修復研究領域(彫刻)博士後期課程修了 お仏壇のはせがわ特別賞受賞 静岡銀行賞受賞 「たからものを探しに」(ポスターハリスギャラリー/渋谷) 保存修復彫刻研究室 教育研究助手として勤務 |
| 2017年 | 「プラセボソワカ」(横浜市民ギャラリーあざみ野) |
| 2018年 | 「木彫三昧」(髙島屋/新宿・横浜) 「MITSUKOSHI×東京藝術大学夏の芸術祭2018」(三越本店/日本橋) 「明日にかける彫刻家たち」(松坂屋/静岡) 「小さなアートのクリスマス展」(髙島屋/新宿) 「ほとけの王国―大分の仏像―」(大分市歴史資料館) |
| 2019年 | 「《雕刻之森與刀下的故事》日本木雕新時代特展」(涅普頓畫廊/台北) 保存修復彫刻研究室 非常勤講師として勤務 |
| 2020年 | 「OneArtTaipei」(涅普頓畫廊/台北) 「与謝野晶子幻想~百選会から広がる美と造形」(高島屋/日本橋) |
| 2021年 | 個展「小島久典展」(高島屋/日本橋・大阪・横浜・新宿 巡回) 「特別展示『仏像工学―追体験と新解釈』」(東京大学総合研究博物館インターメディアテク/丸の内) 「藝大之末裔與未来日本當代彫刻展」(涅普頓畫廊/台北) 「みろく―終わりの彼方弥勒の世界―」(東京藝術大学大学美術館) |
| 2022年 | 「ONEARTTAIPEI」(涅普頓畫廊/台北) 「ARTTAINAN」(涅普頓畫廊/台南) 「WHATZArtFair」(涅普頓畫廊/台北) 「ArtTaichung」(涅普頓畫廊/台中) |
| 現在 | 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻(保存修復彫刻研究室)助教 |
| 2012年 | 国立台湾藝術大学 古蹟藝術修護学系 卒業 |
|---|---|
| 2013年 | 東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 修士課程 入学 |
| 2015年 | 東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 修士課程 修了 東京藝術大学 保存修復彫刻研究室 技術職員 お仏壇のはせがわ賞受賞(第9回) |
| 2017年 | 東京藝術大学 保存修復彫刻研究室 教育研究助手(2017年10月まで) |
| 2018年 | 東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 博士課程 入学 芳泉文化財団研究助成金(2019年度) 台日交流協会奨学金(2020年度) |
| 2021年 | 東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 博士課程 修了 お仏壇のはせがわ特別賞受賞(第12回) 藤白彫刻研究所 契約社員 |
| 2023年 | 東京藝術大学 保存修復彫刻研究室 専門研究員 現在 |
学生
| 1989年 | 中国安徽省で生まれ |
|---|---|
| 2012年 | 浙江省杭州科技学院 アニメーション科 卒業 |
| 2016年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室修士 |
| 2018年 | 同研究室 技術職員 |
| 2020年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室博士課程在籍 |
| 1994年 | 中国湖南省生まれ |
|---|---|
| 2009年 | 中国美術学院附属高校 入学 |
| 2012年 | 中国美術学院附属高校 卒業 |
| 2013年 | 中国美術学院学部 彫刻科 入学 中国美術学院新入生賞 受賞 |
| 2018年 | 中国美術学院学部 彫刻科 卒業 中国美術学院卒業創作及び「林風眠」創作賞 受賞 韓国E.LAND優秀卒業創作賞 受賞 |
| 2020年 | 東京で語学学習 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 入学 |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 修了 第16回「お仏壇のはせがわ賞」 受賞東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 博士後期課程 入学 |
| 1991年 | 中国遼寧省瀋陽市で生まれ |
|---|---|
| 2016年 | 中央美術学院造形学部 彫刻科 卒業 |
| 2019年 | 中央美術学院大学院 彫刻科 修士課程在籍 |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程在籍 修了研究『慈恩寺十二神将のうち卯神将における彫刻制作の計画性とその変更に関する検証』お仏壇のはせがわ賞受賞東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 博士課程在籍 |
| 1995年 | 中国生まれ |
|---|---|
| 2018年 | 中央美術学院学部 工藝科 卒業 |
| 2021年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 入学 |
| 2023年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 修了 |
| 2022年 | 東京造形⼤学造形学部 彫刻専攻 卒業
東京藝術⼤学⼤学院美術研究科 ⽂化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 |
|---|
| 1999年 | 中国北京生まれ |
|---|---|
| 2016年 | カナダに留学 |
| 2023年 | 多摩美術大学 彫刻学科 卒業 |
| 2023年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 入学 |
| 1999年 | 福井県生まれ |
|---|---|
| 2018年 | 福井県立藤島高等学校 卒業 |
| 2024年 | 東京学芸大学教育学部 教育支援課程生涯学習コース 文化遺産教育サブコース 卒業 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程入学 |
| 2000年 | 東京生まれ |
|---|---|
| 2022年 | 横浜国立大学 教育学部 卒業 |
| 2024年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室修士課程 入学 |
| 2020年 | 福岡県立修猷館高等学校 卒業 |
|---|---|
| 2024年 | 京都芸術大学 芸術学部 歴史遺産学科 卒業 |
| 2024年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程入学 |
教員

木製彫刻文化財の保存修復を専門とし、仏像、キリスト教彫刻、古代エジプト木製品などの保存修復を数多く手がける。また、地域文化財の保護活動にも取り組み、各地での地域文化財調査や地域現場での臨床的な保存修復活動、防災や被災文化財の保存修復活動なども行っている。
| 1975年 | 愛知県蒲郡市生まれ |
|---|---|
| 1998年 | 東京藝術大学美術学部彫刻科 卒業 |
| 2000年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻 修士課程修了 |
| 2004年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻 博士後期課程 修了 博士号(文化財)取得 |
| 2004年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻研究室 非常勤講師 |
| 2007年 | 文化財保護・芸術研究助成財団在外研修員としてイタリア・フィレンツェのUniversità Internazionale dell’Arte(国際芸術大学)とOpificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze(国立フィレンツェ貴石加工所および修復研究所) にて研修 |
| 2009年 | 東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター 専任講師・研究員 |
| 2012年 | JICA短期派遣専門家(大エジプト博物館保存修復センター人材育成プロジェクト木材研修担当講師) |
| 2015年 | 木製彫刻文化財保存修復研究所 設立 代表 |
| 2016年 | 一般社団法人木文研 代表理事 |
| 2015年 | JICA短期派遣専門家(大エジプト博物館保存修復センター人材育成プロジェクト テクニカルアドバイザー) |
| 2014年 | 山形大学地域教育文化学部 非常勤講師 |
| 2016年 | 大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト テクニカルチーフアドバイザー |
| 2019年 | 帝京大学文化財研究所 准教授 |
| 2021年4月〜 | 現職 |

| 1988年 | 国立小山工業高等専門学校 機械工学科 卒業 |
|---|---|
| 1990年 | (株)仏教造形研究所 入所 |
| 1994年 | 東京藝術大学 美術学部 デザイン科 卒業 |
| 1997年 | 東京藝術大学大学院 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室 修了 学位取得制作「滋賀県近江八幡市伊崎寺 焼損天部立像 想定復元制作」 (サロン・ド・プランタン賞受賞) |
| 1998年 | (株)仏教造形研究所 彫刻部主任研究員着任 |
| 2002年 | あきかわ造仏所設立 神奈川県川崎市文化財調査員(~2010年3月まで) |
| 現在 | あきかわ造仏所代表 長岡造形大学 非常勤講師(2012年4月~) 東京藝術大学 非常勤講師(2021年4月~) |

| 1968年 | 愛知県に生まれる |
|---|---|
| 1986年 | 日本伝統工芸士 吉田信久氏(富山県井波町)に師事 |
| 2001年 | 第9回木彫フォークアート.おおや(兵庫県)グランプリ受賞 |
| 2006年 | 個展「時の旅・風の景 杉浦誠展」(Lギャラリー) |
| 2009年 | 個展「—鳥の視点-杉浦誠木彫展」(靖山画廊) |
| 2011年 | 東京藝術大学大学院保存修復彫刻研究室 非常勤講師(現在〜) |
| 2012年 | 個展「杉浦誠木彫展」(大丸心斎橋店) |
| 2013年 | 個展「杉浦誠木彫展-鳥の視点-」(日本橋三越本店) |
| 2016年 | 個展「杉浦誠彫刻展」(仙台三越) |

| 1984年 | 香川生まれ |
|---|---|
| 2014年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復(彫刻)博士後期課程 修了 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 教育研究助手 |
| 2016年 | 合同会社 藤白彫刻研究所 運営 |
| 2017年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 非常勤講師 |
| 2021年 | 同研究室 テクニカルインストラクター |
| 2022年 | 同研究室 非常勤講師 |

| 1985年 | 神奈川生まれ |
|---|---|
| 2010年 | 東京藝術大学美術学部 芸術学科 卒業 |
| 2013年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 芸術学専攻 修了 平山郁夫奨学金 受賞 |
| 2016年 | 日本学術振興会 特別研究員(DC2) |
| 2019年 | 早稲田大学図書館資料管理課 特別資料室 常勤嘱託(専門職) |
| 2020年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 美術専攻 博士(学術)修了 あさかぜ賞 受賞 東海大学 非常勤講師 |
| 2021年 | 日本学術振興会 特別研究員(PD) 駒澤大学 非常勤講師 |
| 2022年 | 成城大学 非常勤講師 東京藝術大学 学術インストラクター |
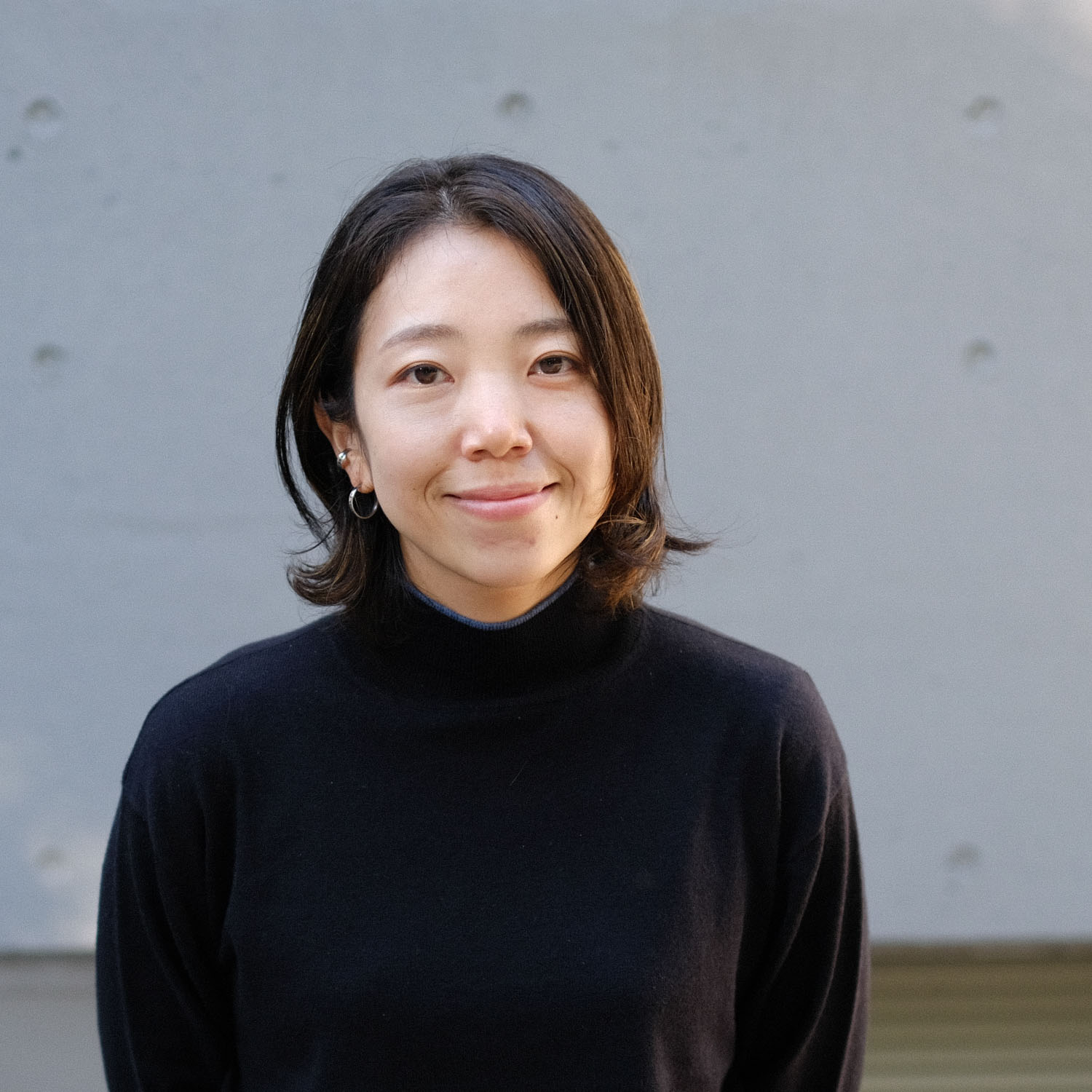
| 1988年 | 東京で生まれ長野に移住する |
|---|---|
| 2014年 | 東京藝術大学美術学部 彫刻科 卒業 卒業制作『そこに居る』東洋文庫賞受賞 |
| 2016年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程在籍 同研究室 研究協力者 |
| 2021年 | 同研究室 教育研究助手 「MITSUKOSHI ✕ 東京藝術大学 夏の芸術祭 2018」作品出品 「MITSUKOSHI ✕ 東京藝術大学 夏の芸術祭 2020」作品出品 フリーで作家活動をはじめる |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 教育研究助手 |
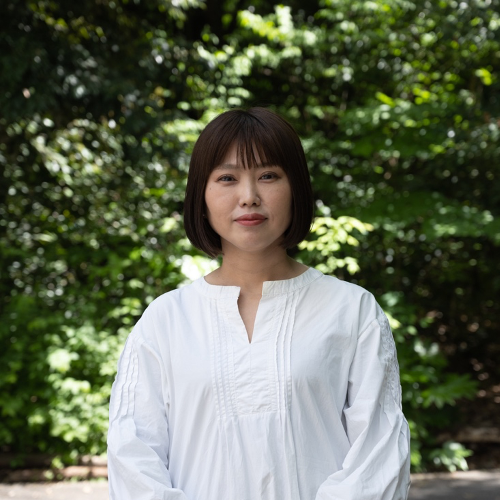
| 2001-2005 | 一橋大学 経済学部 経済学科 |
|---|---|
| 2011-2014 | 東京藝術大学 美術学部 芸術学科 |
| 2014-2016 | 東京藝術大学 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復(油画)修士課程 |
| 2017-2019 | 日本学術振興会 特別研究員(DC2) |
| 2016-2021 | 東京藝術大学 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復(油画) 博士後期課程 あさかぜ賞受賞 |
| 2021-2022 | 東京藝術大学 学術インストラクター |
| 2021-2022 | 文化庁新進芸術家海外研修制度 研修員(ギリシャ) |
| 2021- 現在 | University of West Attica, Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, 研究員 |

| 1986年 | 広島生まれ |
|---|---|
| 2006年 | 東京藝術大学美術学部彫刻科入学 |
| 2010年 | 三菱地所賞受賞
「藝大アーツin東京丸の内三菱地所賞受賞者作品展」(丸ビル/東京) 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻保存修復(彫刻)入学 |
| 2011年 | 「台湾国際木彫藝術交流展」招待出品 |
| 2012年 | お仏壇のはせがわ賞受賞 |
| 2013年 | 「覚の会」(靖山画廊/東京) |
| 2014年 | 「木の系譜―進化する奔流―」(髙島屋/日本橋・大阪・横浜) 「籔内佐斗司とその後継者たち」(松坂屋/名古屋) |
| 2015年 | 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻保存修復研究領域(彫刻)博士後期課程修了 お仏壇のはせがわ特別賞受賞 静岡銀行賞受賞 「たからものを探しに」(ポスターハリスギャラリー/渋谷) 保存修復彫刻研究室 教育研究助手として勤務 |
| 2017年 | 「プラセボソワカ」(横浜市民ギャラリーあざみ野) |
| 2018年 | 「木彫三昧」(髙島屋/新宿・横浜) 「MITSUKOSHI×東京藝術大学夏の芸術祭2018」(三越本店/日本橋) 「明日にかける彫刻家たち」(松坂屋/静岡) 「小さなアートのクリスマス展」(髙島屋/新宿) 「ほとけの王国―大分の仏像―」(大分市歴史資料館) |
| 2019年 | 「《雕刻之森與刀下的故事》日本木雕新時代特展」(涅普頓畫廊/台北) 保存修復彫刻研究室 非常勤講師として勤務 |
| 2020年 | 「OneArtTaipei」(涅普頓畫廊/台北) 「与謝野晶子幻想~百選会から広がる美と造形」(高島屋/日本橋) |
| 2021年 | 個展「小島久典展」(高島屋/日本橋・大阪・横浜・新宿 巡回) 「特別展示『仏像工学―追体験と新解釈』」(東京大学総合研究博物館インターメディアテク/丸の内) 「藝大之末裔與未来日本當代彫刻展」(涅普頓畫廊/台北) 「みろく―終わりの彼方弥勒の世界―」(東京藝術大学大学美術館) |
| 2022年 | 「ONEARTTAIPEI」(涅普頓畫廊/台北) 「ARTTAINAN」(涅普頓畫廊/台南) 「WHATZArtFair」(涅普頓畫廊/台北) 「ArtTaichung」(涅普頓畫廊/台中) |
| 現在 | 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻(保存修復彫刻研究室)助教 |
| 2012年 | 国立台湾藝術大学 古蹟藝術修護学系 卒業 |
|---|---|
| 2013年 | 東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 修士課程 入学 |
| 2015年 | 東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 修士課程 修了 東京藝術大学 保存修復彫刻研究室 技術職員 お仏壇のはせがわ賞受賞(第9回) |
| 2017年 | 東京藝術大学 保存修復彫刻研究室 教育研究助手(2017年10月まで) |
| 2018年 | 東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 博士課程 入学 芳泉文化財団研究助成金(2019年度) 台日交流協会奨学金(2020年度) |
| 2021年 | 東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 博士課程 修了 お仏壇のはせがわ特別賞受賞(第12回) 藤白彫刻研究所 契約社員 |
| 2023年 | 東京藝術大学 保存修復彫刻研究室 専門研究員 現在 |
| 1995年 | 中国生まれ |
|---|---|
| 2018年 | 中央美術学院学部 工藝科 卒業 |
| 2021年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 入学 |
| 2023年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 修了 |
学生
| 1989年 | 中国安徽省で生まれ |
|---|---|
| 2012年 | 浙江省杭州科技学院 アニメーション科 卒業 |
| 2016年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室修士 |
| 2018年 | 同研究室 技術職員 |
| 2020年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室博士課程在籍 |
| 1994年 | 中国湖南省生まれ |
|---|---|
| 2009年 | 中国美術学院附属高校 入学 |
| 2012年 | 中国美術学院附属高校 卒業 |
| 2013年 | 中国美術学院学部 彫刻科 入学 中国美術学院新入生賞 受賞 |
| 2018年 | 中国美術学院学部 彫刻科 卒業 中国美術学院卒業創作及び「林風眠」創作賞 受賞 韓国E.LAND優秀卒業創作賞 受賞 |
| 2020年 | 東京で語学学習 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 入学 |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 修了 第16回「お仏壇のはせがわ賞」 受賞東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 博士後期課程 入学 |
| 1991年 | 中国遼寧省瀋陽市で生まれ |
|---|---|
| 2016年 | 中央美術学院造形学部 彫刻科 卒業 |
| 2019年 | 中央美術学院大学院 彫刻科 修士課程在籍 |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程在籍 修了研究『慈恩寺十二神将のうち卯神将における彫刻制作の計画性とその変更に関する検証』お仏壇のはせがわ賞受賞東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 博士課程在籍 |
| 2022年 | 東京造形⼤学造形学部 彫刻専攻 卒業
東京藝術⼤学⼤学院美術研究科 ⽂化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 |
|---|
| 1999年 | 中国北京生まれ |
|---|---|
| 2016年 | カナダに留学 |
| 2023年 | 多摩美術大学 彫刻学科 卒業 |
| 2023年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 入学 |
教員

木製彫刻文化財の保存修復を専門とし、仏像、キリスト教彫刻、古代エジプト木製品などの保存修復を数多く手がける。また、地域文化財の保護活動にも取り組み、各地での地域文化財調査や地域現場での臨床的な保存修復活動、防災や被災文化財の保存修復活動なども行っている。
| 1975年 | 愛知県蒲郡市生まれ |
|---|---|
| 1998年 | 東京藝術大学美術学部彫刻科 卒業 |
| 2000年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻 修士課程修了 |
| 2004年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻 博士後期課程 修了 博士号(文化財)取得 |
| 2004年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復彫刻研究室 非常勤講師 |
| 2007年 | 文化財保護・芸術研究助成財団在外研修員としてイタリア・フィレンツェのUniversità Internazionale dell’Arte(国際芸術大学)とOpificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze(国立フィレンツェ貴石加工所および修復研究所) にて研修 |
| 2009年 | 東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター 専任講師・研究員 |
| 2012年 | JICA短期派遣専門家(大エジプト博物館保存修復センター人材育成プロジェクト木材研修担当講師) |
| 2015年 | 木製彫刻文化財保存修復研究所 設立 代表 |
| 2016年 | 一般社団法人木文研 代表理事 |
| 2015年 | JICA短期派遣専門家(大エジプト博物館保存修復センター人材育成プロジェクト テクニカルアドバイザー) |
| 2014年 | 山形大学地域教育文化学部 非常勤講師 |
| 2016年 | 大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト テクニカルチーフアドバイザー |
| 2019年 | 帝京大学文化財研究所 准教授 |
| 2021年4月〜 | 現職 |

| 1986年 | 広島生まれ |
|---|---|
| 2006年 | 東京藝術大学美術学部彫刻科入学 |
| 2010年 | 三菱地所賞受賞
「藝大アーツin東京丸の内三菱地所賞受賞者作品展」(丸ビル/東京) 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻保存修復(彫刻)入学 |
| 2011年 | 「台湾国際木彫藝術交流展」招待出品 |
| 2012年 | お仏壇のはせがわ賞受賞 |
| 2013年 | 「覚の会」(靖山画廊/東京) |
| 2014年 | 「木の系譜―進化する奔流―」(髙島屋/日本橋・大阪・横浜) 「籔内佐斗司とその後継者たち」(松坂屋/名古屋) |
| 2015年 | 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻保存修復研究領域(彫刻)博士後期課程修了 お仏壇のはせがわ特別賞受賞 静岡銀行賞受賞 「たからものを探しに」(ポスターハリスギャラリー/渋谷) 保存修復彫刻研究室 教育研究助手として勤務 |
| 2017年 | 「プラセボソワカ」(横浜市民ギャラリーあざみ野) |
| 2018年 | 「木彫三昧」(髙島屋/新宿・横浜) 「MITSUKOSHI×東京藝術大学夏の芸術祭2018」(三越本店/日本橋) 「明日にかける彫刻家たち」(松坂屋/静岡) 「小さなアートのクリスマス展」(髙島屋/新宿) 「ほとけの王国―大分の仏像―」(大分市歴史資料館) |
| 2019年 | 「《雕刻之森與刀下的故事》日本木雕新時代特展」(涅普頓畫廊/台北) 保存修復彫刻研究室 非常勤講師として勤務 |
| 2020年 | 「OneArtTaipei」(涅普頓畫廊/台北) 「与謝野晶子幻想~百選会から広がる美と造形」(高島屋/日本橋) |
| 2021年 | 個展「小島久典展」(高島屋/日本橋・大阪・横浜・新宿 巡回) 「特別展示『仏像工学―追体験と新解釈』」(東京大学総合研究博物館インターメディアテク/丸の内) 「藝大之末裔與未来日本當代彫刻展」(涅普頓畫廊/台北) 「みろく―終わりの彼方弥勒の世界―」(東京藝術大学大学美術館) |
| 2022年 | 「ONEARTTAIPEI」(涅普頓畫廊/台北) 「ARTTAINAN」(涅普頓畫廊/台南) 「WHATZArtFair」(涅普頓畫廊/台北) 「ArtTaichung」(涅普頓畫廊/台中) |
| 現在 | 東京藝術大学大学院文化財保存学専攻(保存修復彫刻研究室)助教 |

| 1988年 | 国立小山工業高等専門学校 機械工学科 卒業 |
|---|---|
| 1990年 | (株)仏教造形研究所 入所 |
| 1994年 | 東京藝術大学 美術学部 デザイン科 卒業 |
| 1997年 | 東京藝術大学大学院 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室 修了 学位取得制作「滋賀県近江八幡市伊崎寺 焼損天部立像 想定復元制作」 (サロン・ド・プランタン賞受賞) |
| 1998年 | (株)仏教造形研究所 彫刻部主任研究員着任 |
| 2002年 | あきかわ造仏所設立 神奈川県川崎市文化財調査員(~2010年3月まで) |
| 現在 | あきかわ造仏所代表 長岡造形大学 非常勤講師(2012年4月~) 東京藝術大学 非常勤講師(2021年4月~) |

| 1968年 | 愛知県に生まれる |
|---|---|
| 1986年 | 日本伝統工芸士 吉田信久氏(富山県井波町)に師事 |
| 2001年 | 第9回木彫フォークアート.おおや(兵庫県)グランプリ受賞 |
| 2006年 | 個展「時の旅・風の景 杉浦誠展」(Lギャラリー) |
| 2009年 | 個展「—鳥の視点-杉浦誠木彫展」(靖山画廊) |
| 2011年 | 東京藝術大学大学院保存修復彫刻研究室 非常勤講師(現在〜) |
| 2012年 | 個展「杉浦誠木彫展」(大丸心斎橋店) |
| 2013年 | 個展「杉浦誠木彫展-鳥の視点-」(日本橋三越本店) |
| 2016年 | 個展「杉浦誠彫刻展」(仙台三越) |
| 1984年 | 香川生まれ |
|---|---|
| 2014年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復(彫刻)博士後期課程 修了 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 教育研究助手 |
| 2016年 | 合同会社 藤白彫刻研究所 運営 |
| 2017年 | 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 非常勤講師 |
| 2021年 | 同研究室 テクニカルインストラクター |
| 2022年 | 同研究室 非常勤講師 |

| 1985年 | 神奈川生まれ |
|---|---|
| 2010年 | 東京藝術大学美術学部 芸術学科 卒業 |
| 2013年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 芸術学専攻 修了 平山郁夫奨学金 受賞 |
| 2016年 | 日本学術振興会 特別研究員(DC2) |
| 2019年 | 早稲田大学図書館資料管理課 特別資料室 常勤嘱託(専門職) |
| 2020年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 美術専攻 博士(学術)修了 あさかぜ賞 受賞 東海大学 非常勤講師 |
| 2021年 | 日本学術振興会 特別研究員(PD) 駒澤大学 非常勤講師 |
| 2022年 | 成城大学 非常勤講師 東京藝術大学 学術インストラクター |
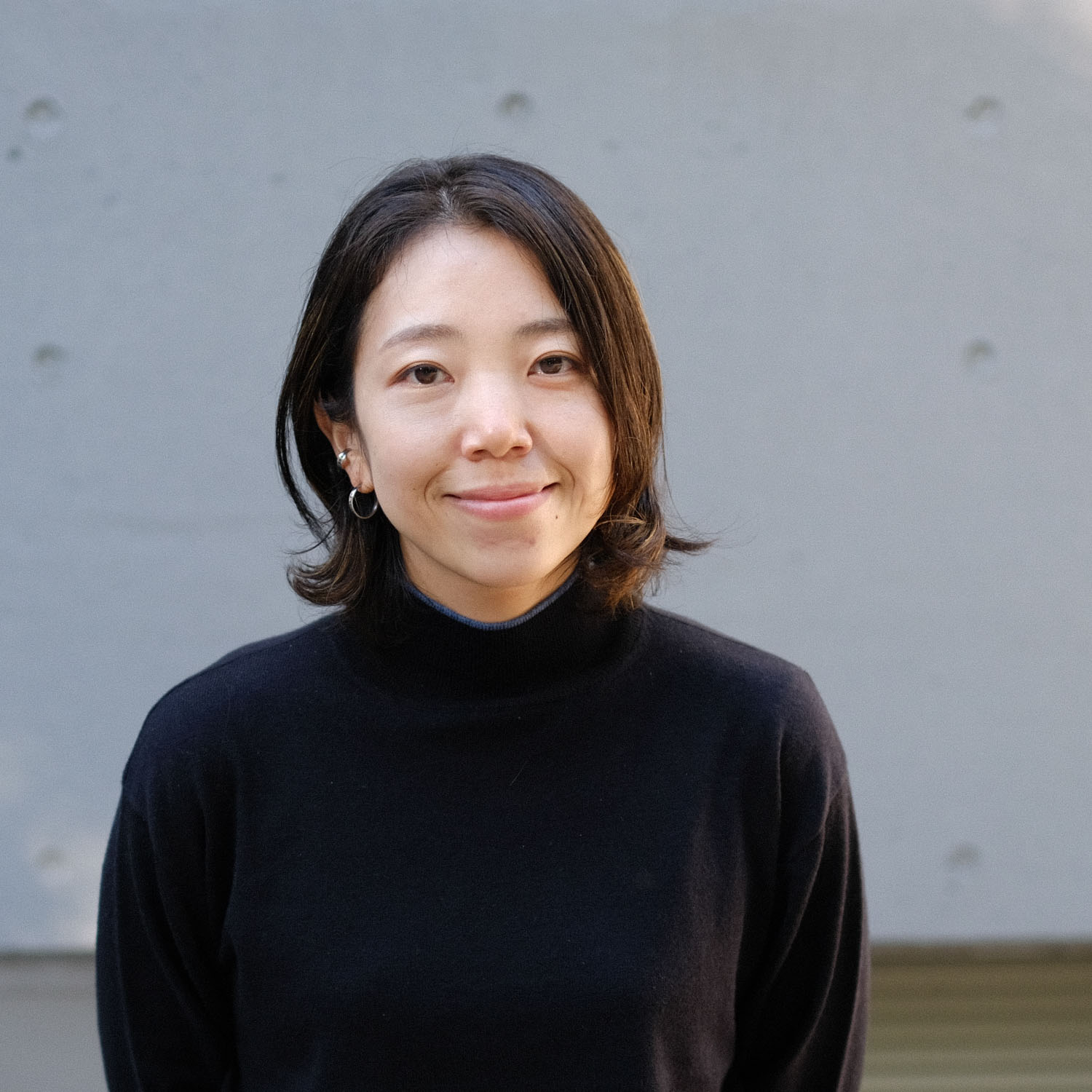
| 1988年 | 東京で生まれ長野に移住する |
|---|---|
| 2014年 | 東京藝術大学美術学部 彫刻科 卒業 卒業制作『そこに居る』東洋文庫賞受賞 |
| 2016年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程在籍 同研究室 研究協力者 |
| 2021年 | 同研究室 教育研究助手 「MITSUKOSHI ✕ 東京藝術大学 夏の芸術祭 2018」作品出品 「MITSUKOSHI ✕ 東京藝術大学 夏の芸術祭 2020」作品出品 フリーで作家活動をはじめる |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 教育研究助手 |
| 1996年 | 香川県に生まれる |
|---|---|
| 2020年 | 東京藝術大学美術学部 彫刻科 卒業 卒業制作『オフの日』美術学部杜の会 杜賞 三菱地所賞 |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程在籍 同研究室 技術職員 |
学生
| 2007年 | 中国 中央美術学院 彫刻学部 入学 |
|---|---|
| 2011年 | フランス リオン国立美術学院 交換留学生 |
| 2013年 | 中国 中央美術学院 彫刻学部 卒業 |
| 2018年 | 東京藝術大学文化財保存学修士課程 入学 |
| 2020年 | 東京藝術大学文化財保存学修士課程 卒業 東京藝術大学お仏壇のはせがわ賞 芳泉文化財団研究助成金(2020年・2021年・2022年) |
| 2021年 | 三島海雲記念財団学術奨励金 |
| 2022年 | 日本学術振興会特別研究員 日本学術振興会特別研究員奨励費 |
| 1989年 | 中国安徽省で生まれ |
|---|---|
| 2012年 | 浙江省杭州科技学院 アニメーション科 卒業 |
| 2016年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室修士 |
| 2018年 | 同研究室 技術職員 |
| 2020年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室博士課程在籍 |
| 1994年 | 中国湖南省生まれ |
|---|---|
| 2009年 | 中国美術学院附属高校 入学 |
| 2012年 | 中国美術学院附属高校 卒業 |
| 2013年 | 中国美術学院学部 彫刻科 入学 中国美術学院新入生賞 受賞 |
| 2018年 | 中国美術学院学部 彫刻科 卒業 中国美術学院卒業創作及び「林風眠」創作賞 受賞 韓国E.LAND優秀卒業創作賞 受賞 |
| 2020年 | 東京で語学学習 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 入学 |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 修了 第16回「お仏壇のはせがわ賞」 受賞東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 博士後期課程 入学 |
| 1991年 | 中国遼寧省瀋陽市で生まれ |
|---|---|
| 2016年 | 中央美術学院造形学部 彫刻科 卒業 |
| 2019年 | 中央美術学院大学院 彫刻科 修士課程在籍 |
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程在籍 修了研究『慈恩寺十二神将のうち卯神将における彫刻制作の計画性とその変更に関する検証』お仏壇のはせがわ賞受賞東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 博士課程在籍 |
| 2020年 | 東京藝術⼤学美術学部 彫刻科 卒業 |
|---|---|
| 2021年 | 東京藝術⼤学⼤学院美術研究科 ⽂化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 ⼊学 |
| 1995年 | 中国で生まれた |
|---|---|
| 2018年 | 中央美術学院学部 工藝科 卒業 |
| 2021年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程 入学 |
| 2022年 | 東京造形⼤学造形学部 彫刻専攻 卒業
東京藝術⼤学⼤学院美術研究科 ⽂化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 |
|---|
| 2022年 | 金沢美術工芸大学 美術工芸学部 工芸科 卒業 |
|---|---|
| 2022年 | 東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室 修士課程在籍 |
沿革

| 1887年 | 岡倉天心を初代校長として東京美術学校を前身とし本学設立 |
|---|---|
| 1898年 | 日本美術院(現・公益財団法人日本美術院)を設立 |
| 1906年 | 日本美術院第二部として奈良に仏像修理事業を専門とする 美術院(現・公益財団法人美術院国宝修理所)を創設 |
| 1967年 | 東京藝術大学(大学院)に設立された保存修復技術講座に本研究室設置 西村公朝(当時、美術院国宝修理所所長を兼務)を主任教員として研究室をスタート |
| 1987〜2004年 | 長澤 市郎 勤務 |
| 1995年 | 大学院美術研究科の独立専攻として現在の文化財保存学専攻が設立 |
| 2004〜2020年 | 籔内 佐斗司 勤務 |
| 2021年〜 | 岡田 靖 勤務 |


